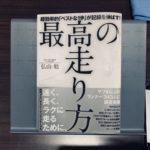マラソンシーズン真只中の2月、それぞれが目標レースに向け練習に励んでいると思います。
現在は週2回のポイント練習を積むルーティーンですが、それでもその間を埋める緩ジョグは、箸休めの意味合いを含みます。
これはこれで必要な時間であり、近所の川沿いをリラックス (キロ6分以下) して走っていると、何度か車道と交差する横断歩道が現れます。
そんな信号のない横断歩道において、昔と違い最近ほとんどの車が停止して渡らせてもらえると思いませんか?私が走り始めた20数年前とは隔世の感があります。
スポンサーリンク
信号の無い歩道で停止してくれる車両が増えたと実感

走り始めた2000年初頭と比べるとランニングシーンは大きく変わっています。
ランナーそのものの絶対数が増えたことや、夜間はライト持参ランナーが増えたのはもちろんのこと、これは変わったと断言できる事象が信号の無い歩道でほとんどの車が停止して渡らせてもらえることです。
当時は歩道でしばらく待っていても停止する車両は少なく、タイミングを測って渡らなければなりませんでした。
教習所で習う「歩行者優先」とは、名ばかりのものでしかありませんでした。
きっかけ

東京オリンピック聖火台 (国立競技場)
きっかけは2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、他先進国では浸透しているが日本では希薄だった歩行者優先が強化されたことです。
このとき謷視庁から全国へ通達があり、道路交通法第38条にあるように、「横断歩道を渡ろうとする人がいた場合は、車は停止し歩行者の進行を妨げてはならない。」との取り締まりが徹底されました。
これが歩行者優先の意識を持つドライバーが増えた最大の理由です。
赤信号と同等

信号のない横断歩道に歩行者がいる場合、そこは赤信号であると同等な扱いとなります。よって赤だから必ず止まらなければならないのです。
でもでも運転する人なら分かると思いますが、特に年配者に多い傾向として「お先にどうぞ」と車の進行を促されるケースです。
「どうもどうも」などと車を走らせてしまうと1発で交通違反の取り締まりの餌食となります。
ネット情報では警察に対して譲ってくれたからの言い分は通用せず、譲られても譲り返さなければならないとのことです。
なぜなら歩行者がいる横断歩道は上述した通り赤信号と同意だから。赤信号で譲られたからってアクセルを踏むドライバーはいません。
ただこの辺の線引きは歩行者の意思もあるので問答無用はいささか厳し過ぎるとも思えます。
捕まりたくない

以上の理由でオリンピック以降取締りが厳しくなり、一時停止不停止の取り締まり同様 (過去2回確保されるw)、いつどこで警察が張っているか検討もつかないからドライバーとしては厄介なのです。
歩行者優先を念頭に入れて優しい運転を心掛けていますが、絶対に捕まりたくないから停止するが本音ではないでしょうか。
ランナーもドライバーも気持ちよく走れれば
私自身運転中に歩行者が横断しようとする場面ではもちろん停止します。
そんな中周りが見えていないのか、歩行者は全くの無視で走り去っていく車両にもでくわします。 (捕まってしまえ!の念)
また自身がランニング中で停止してもらえたら、必ずドライバーへお礼ジェスチャーを添えて速やかに走り去るようにしています。歩行者 (ランナー) 目線でも運転者目線でも交通ルールは守って然るべきなのです。
いずれにしても信号のない横断歩道の交通法規は、ランナーはいつまでも渡れないジレンマの軽減となり、またドライバーにとっては交通ルールを遵守していれば捕まることはありません。ひいては加害者と被害者リスクの軽減につながるという話でした。

東京マラソン最後の直線にも横断歩道 (丸の内仲通り)